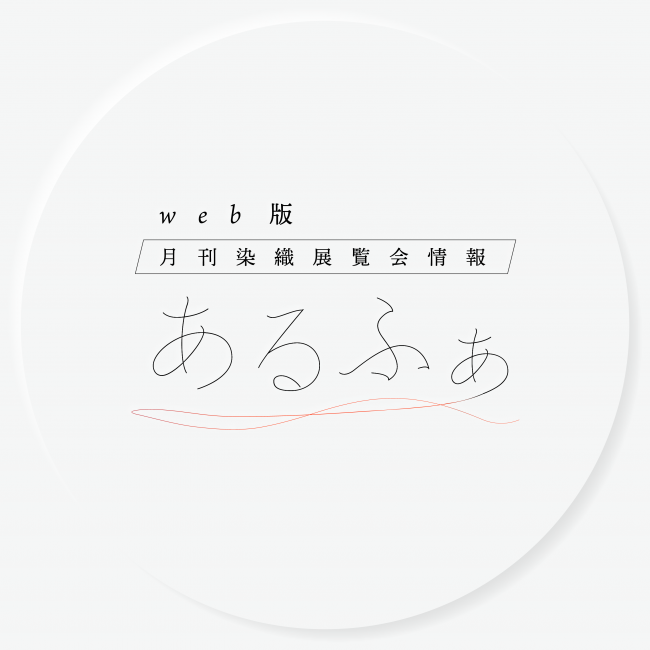史跡旧崇広堂
☎/0595(24)6090
三重県伊賀市上野丸之内78の1
9時~16時30分
火曜休み
第60回記念日本現代工芸美術展
▼5月26日~6月5日
→1961年に創設された現代工芸美術家協会の公募展。「工芸の本義は作家の美的イリュウジョンを基幹として所謂工芸素材を駆使し、その造型効果に依る独特の美の表現をなすもので、その制作形式の立体的たると平面的たるとをとわず工芸美を追求することにある」とする「主張」を掲げる。役員、会員、一般入選者による、陶磁・染織・漆芸・人形・ガラス・七宝などの作品を展示
マコンデ美術館
☎/0596(42)1192
三重県伊勢市二見町松下1799
9時~17時
火曜休み
マコンデ族の絵画展(バチック)
▼3月16日~7月18日
→マコンデ族は、東アフリカのタンザニア、モザンビーク両国国境に広がる5,000平方キロメートルの広大な高原地帯、マコンデ高原(海抜500m~800m)に住むバンドゥ族の一員。マコンデ族の発祥の地はナイジェリアまたはカメルーン地方とされ、彼らは、コンゴやザンビアを得てマコンデ高原に定住した農耕民族。その大自然の高原で暮らしてきたマコンデ族の生活風景を描いたローケツ染め(バチック)作品を展示
彦根城博物館
☎/0749(22)6100
滋賀県彦根市金亀町1の1
8時30分~17時(入館30分前)
会期中無休
国宝・彦根屏風
▼4月15日~5月15日
→近世風俗画の傑作として知られる「彦根屏風」を展示。寛永年間頃の、小袖や髷、煙管や刀など、当時の華やかな風俗が緻密な筆致で描かれており、近世初期の服飾や文様などを知る上で貴重な資料
大阪日本民芸館
☎/06(6877)1971
大阪府吹田市千里万博公園10の5
10時~17時(入館30分前)
水曜(祝日は開館)、5月6日休み
大阪日本民芸館50周年記念 今のかたち―西日本の民藝―
▼3月5日~7月18日
→1972年に「民藝運動の西の拠点」として開館した大阪日本民芸館は、今年で50年の節目を迎える。同展ではこれを記念して、関西から沖縄までの西日本で活躍する現役の作り手、約100名の作品を一堂に展示する。柳宗悦らが創始した民藝運動は、彼らが見出した美の紹介を主軸に、手仕事の復権や各地の民芸館を拠点とした普及活動など多彩な広がりをみせた。その活動の一つとして早くから目指されていたのが、時代に即した新作を生み出しそれらを生活に結ぶことであった。こうした民藝運動には草創期から多くの作り手が参加し、担い手として活躍する一方で、彼らもまたその美意識を自らの制作に生かしてきた。そして現在でも、様々な立場、世代、あるいは地域性や制作の分野といった異なる状況の中で、それぞれに民藝と向き合いながら優れた品物を生み出している。民藝という言葉のもとに集った現代の作り手達による「今のかたち」、その多様性や魅力を150点以上の作品を通して紹介
ギャラリー猫亀屋
☎/072(425)4883
大阪府泉南郡岬町淡輪4193の2
10時~17時
火・水曜休み
高木光司展
▼4月23日~5月1日
→テキスタイルアート・インスタレーション
菅野健一展
▼5月7日~15日
→テキスタイルアート・染色
兵庫県公館
☎/078(362)3823
神戸市中央区下山手通4の4の1
9時~17時
土・日曜・祝日休み
たじまゆきひこ展
▼2月18日~5月14日<展示室7「兵庫の文化」>
→淡路市在住の型絵染作家・絵本作家の作品を展示
神戸ファッション美術館
☎/078(858)0050
神戸市東灘区向洋町中2の9の1
10時~18時(入館30分前)
月曜休み(祝日の場合翌休)
華麗なる宝塚歌劇衣装の世界
▼4月16日~6月12日
→1914年の初公演以来、今日も人気を集める宝塚歌劇。その宝塚歌劇の世界を、衣装を通して紹介する。宝塚歌劇の衣装は、歌劇の題材が国際色豊かで時代背景も様々なため、多様な生地素材やスタイル、宝塚歌劇ならではの華やかなデザインが特徴的。華麗な舞台を支えるプロフェッショナルな技術も垣間見ながら、帽子や靴、デザイン画など、約120点を展示。舞台衣装という枠にとどまらない個性豊かで幅広いジャンルの衣装を通して、「タカラヅカの衣装」の面白さ、奥深さを展開する
白鶴美術館
☎/078(851)6001
神戸市東灘区住吉山手6の1の1
10時~16時30分(入館30分前)
月曜休み(祝日の場合翌休)
白鶴コレクション探訪 ペルシア絨毯編―メダリオンデザイン+総柄文様―
▼4月23日~6月5日<新館>
→二つのテーマで近代ペルシア絨毯を展示。ひとつは、メダリオン・デザインの絨毯。絨毯の中央に大きく配されたメダル形が迫力のある華やかな印象を醸し出し、ペルシア絨毯の代名詞ともなっている。もうひとつは総柄文様の絨毯。ペルシアの絨毯は繊細な文様構成が多いことでも知られている。正確に反復する文様が生み出す精緻な美しさを紹介
市立伊丹ミュージアム
☎/072(772)5959
兵庫県伊丹市宮ノ前2の5の20
10時~18時(入館30分前)
月曜休み(祝日の場合は翌休)
丹波の工芸—杜のいろ
▼4月22日~6月5日
→兵庫丹波を中心に活動する工芸作家17名の作品を一堂に展示。丹波焼、丹波布のほかガラスや版画など多彩な作品を紹介する
姫路市書写の里・美術工芸館
☎/079(267)0301
兵庫県姫路市書写1223
10時~17時(入館30分前)
月曜休み(祝日の場合翌休)
姉妹都市提携50周年・鳥取の美術工芸と民藝
▼4月16日~6月12日
→姫路市と鳥取市との歴史的な結びつきは古く、1600(慶長5)年に姫路城主(播磨姫路藩初代藩主)池田輝政の弟である池田長吉が鳥取城主(因幡鳥取藩初代藩主)となった。また1616(元和2)年に第3代姫路藩主となった池田光政は、翌年には鳥取藩主となり鳥取城下町の基盤を整備した。2022年には姫路市と鳥取市が姉妹都市提携(1972年3月8日)を締結してから50周年を迎えることを記念し、鳥取市の美術工芸や歴史資料、県下の民藝、郷土玩具など60点を紹介する
奈良県立美術館
☎/0742(23)1700
奈良市登大路町10の6
9時~17時(入館30分前)
月曜休み(祝日の場合翌休)
寿ぎのきもの ジャパニーズ・ウェディング―日本の婚礼衣裳―
▼4月23日~6月19日
→婚礼は、人生において最も華やかな通過儀礼のひとつと言える。それゆえ、婚礼の儀式には祈りと喜びの感情が満ちあふれている。そしてその心情を表現するために、花嫁を美しく彩る婚礼衣裳や、婚儀に用いられる様々な調度品、そしてその場を演出するありとあらゆるものには、幸せを祈る色や形、模様が用いられた。同展では、とりわけこうしたことが、美しくも洗練された形で行われていた江戸時代から昭和初期にかけての女性の婚礼衣裳や婚礼のしつらえを紹介する。婚礼に対する日本人の思いと考え方が、これらの品々には表されていて、現代においては遠いものになりつつある、美しい祝いの姿をそこに見ることができる。作品を通して日本における吉祥のイメージを紹介する
天理大学付属参考館
☎/0743(63)8414
奈良県天理市守目堂町250
9時30分~16時30分(入館30分前)
4月28日、火曜休み(祝日の場合翌平日休)
エジプト・カイロの大衆文化―1959年のタイムカプセル―
▼4月15日~6月6日
→1959年1月、後にアラビア語の教授となる田中四郎(1921~2017)は、エジプトの地に初めて足を踏み入れ、カイロでの1年間の留学生活の合間に、当地に暮らす一般の人々が使用する、ありとあらゆる生活道具を収集し、同館にその品々がもたらされた。同展は、63年の時を経て、選りすぐりの品々を初めて一堂に公開するものであり、1959年当時にエジプトで暮らしていた人々の日常を封じ込めた「タイムカプセル」を開くという試みでもある。多種多様な展示品から垣間見えてくるのは、一昔前のエジプト社会の生き生きとした姿。アラビア語を話し、イスラームを信仰する人々の生活様式は、日本人と比べる場合、異なる部分がたくさんあるが、共通点も決して少なくない。エキゾチックでありながら、ノスタルジックな雰囲気も漂う展示品を通じて、エジプト社会の根底にある基層文化や精神世界を紹介する